不登校や母子登校に悩む親御さんは多く、家庭での対応に困っている方が少なくありません。
私たち「みちびき」ではこれまで支援者として多くの親御さん達やお子さんからのSOSをたくさん聞いてきました。
みなさんどの方法が我が子に合うのかを模索され、悩まれています。
親の対応を子どもに合った形に変える家庭教育が子どもの心理的なサポートや学校復帰への力になることもありますので、家庭教育が家庭にどんな効力を与えるのか見ていきましょう!
家庭教育とは

家庭教育は、すべての教育の出発点。
家族のふれ合いを通して、子供が、基本的な生活習慣や生活能力、人に対する信頼感、豊かな情操、他人に対する思いやり、基本的倫理観、自尊心や自立心、社会的なマナーなどを身につけていく上で重要な役割を果たしています。
引用:家庭教育ってなんだろう? | 子供たちの未来をはぐくむ 家庭教育 (mext.go.jp)
こちらの引用にもありますように、家庭教育とは家庭での日常的な関わりや教育を通じて、子どもの成長を支えることを指します。
家庭の役割の重要性

学校に行かない状況でも、家庭は子どもにとって心の拠り所です。
子どもが学校に行く・行かないに関係なく、家庭では子どもが安心して過ごせるための家庭教育が重要になってきます。
人間誰しもが得意・不得意などがあります。きっと、このブログ記事を読んでおられる親御さん達もあると思います。
それ自体はごく自然のことであり問題はないのですが、私たちがよく見ている不登校や母子登校など登校に影響が出ているお子さんや、親子関係で悩まれているご家庭のお子さんを見ているとお子さんの不得意な部分がフォーカスされ過ぎて学校などの社会に不適応を起こしてしまっているという状態であることは多く見受けられます。
不得意や苦手な部分を完全に「できる」形にしましょうというお話ではなく、学校生活など社会において不適応を起こしている状態なのであれば、そこをフォローする方法や考え方・捉え方を家庭の中で培っていく流れを作るイメージを持っていただけるといいと思います。
それでは、具体的に親としてできるサポートを見ていきましょう。
家庭教育でできる具体的なサポート方法

コミュニケーションの取り方
学校などの社会に不適応を起こしてしまう子ども達は、学校生活の中で困っていること・不安に感じていることなどが多いです。
それらを普段から話してくれる子であればある程度親御さんも何かあっても対応しやすい部分がありますが、普段から話さない子も実際少なくありません。
どの様なタイプのお子さんであっても、子どもが話してきたときに親御さん側がしっかり聴いてあげる、受け止めてあげるという対応が非常に大切になってきます。
特に親御さんがよくしてしまいがちな対応としては、子どもから「学校行きたくない・・・。」とネガティブな発言をしてきた時に「何言ってるの?いい加減にしなさいよ!そんなの許されるわけないじゃない!」などと言ってしまうことです。
こういいたくなるお気持ちも分からなくはないですが、子どもはまず自分の気持ちや考えを親御さんに受け止めてもらいたい、共感してほしいと思っています。
共感できる・できないは子どもの発言内容によって変わってくると思いますので、まずは子どもの発言を受け止めてあげるという部分を意識していただけるとよいと思います。
子どもの自己肯定感を育む方法
登校が不安定になっていいる子ども達は殆ど自己肯定感が低くなってしまう傾向が多いです。
やはり多くの子ども達が当たり前のように学校に行っているという事実は理解している子が殆どですから、「みんなができていることが私(僕)はできない。」とネガティブな捉え方になりやすいのだと思われます。
そのため、自己肯定感も低くなってしまいやすいのでしょう。
そういう状況になった子どもを多くの親御さんはすぐに察知され、どうしたらいいのか?と悩まれます。そしてネットや書籍にて「自己肯定感を上げる方法」などと調べてご家庭で実践される方が多いようです。
ただ、多くの親御さんが「自己肯定感を上げるためには成功体験を積ませればいいのだ」という捉え方に落ちつき、子どもに成功体験をさせることやその後親御さんから褒める点ばかりに注目して対応されることも少なくありません。
私たちが常々親御さんにお伝えしていることがあります。

成功体験も大事ですが、失敗体験がダメという話ではありません。
子どもが失敗したのであれば、その次が成長できる大事なポイントになります。
成功するためにはどうしたらいいのか親御さんがサポートしてあげつつ、子どもが親がいない状態でも成功体験に変換できるような流れを目指していきたいですね。
確かに成功体験も素晴らしいですし、自己肯定感アップにつながります。
しかし、そこだけに注力するのではなく、子ども自身が自分で成功体験につなげられるような力を身に着けることが大事であると考えます。
そのサポートができるような家庭環境を整えていくことが賢明であると思います。
家庭教育がもたらす長期的な効果

子どもの心の安定と信頼関係の向上
家庭でしっかり子どもを支えられる環境が整っていると、子どもは安心して過ごすことができます。
これは今の日本では当たり前になり過ぎている部分が大きいのかもしれませんが、子どもの成長過程において安心できる場所(家庭)がある・人(親御さんなど)がいるということは大きな影響を与えます。
心理学でも「安心」というのは人間の5大欲求の1つとされています。(マズローの欲求5段階説)
ここが安定していないと、子どもは自分に自信を持ちにくいとも言われています。
親御さんが子ども達のことを信じて見守ってあげていると、それは子ども側にも伝わります。
子ども達は親御さんからの眼差しや雰囲気から「自分のことを信じてくれている」ということを察知すると、それが次第に根拠のない自信につながっていくのです。そして子ども達は様々な新しい出来事に対しても挑戦しようという気持ち(自己効力感)を持って行動するようになるのです。
家族間の信頼関係が深まれば、子どもがもし困ったことなどに直面しても親御さんを頼る流れは作りやすいでしょう。
誰もが信頼していない人に助けを求めるということはあまり考えにくいですからね。
親子で仲良くあれ、という話ではなく(仲がいいに越したことはありませんが)家族間の信頼関係を築くということが大事です。
社会復帰や学校復帰への準備
家庭内で子どもが自立や社会性を身に着けられるような環境が整っていると、不登校状態などから学校に復帰する場面で躓き難いということは言えるでしょう。
実際、私たちの支援で家庭教育を学ばれたご家庭では、一筋縄とは言いませんが子どもが再び不適応を起こして社会から断絶してしまう状態を避けることはできています。
学校に行く・行かないだけでなく、いずれ子ども達は成長して社会の中で生活していかなければなりません。そこをしっかり意識して子どもに対応していくことが大事であると思います。
家庭教育を通じて育む「生きる力」
「生きる力」とは、文部科学省の学習指導要領にも明記されています。
学校で学んだことが、子供たちの「生きる力」となって、
明日に、そしてその先の人生につながってほしい。
これからの社会が、どんなに変化して予測困難になっても、
自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、
それぞれに思い描く幸せを実現してほしい。
そして、明るい未来を、共に創っていきたい。
「生きる力」とは、学校で求められる【自分で考え、決断する力】が必要なのだと考えます。
その力が低いお子さんは、学校社会で不適応を起こしやすいとも言えます。
どうご家庭で培うことができるのかというのは、個々のご家庭によって変わる部分もありますので、お子さんに合った対応を考えてあげることが大事になるでしょう。
目先のことだけでなく、子ども達の将来の人生をイメージしながら対応していきたいものですね。
まとめ:親としてできる一歩を踏み出す
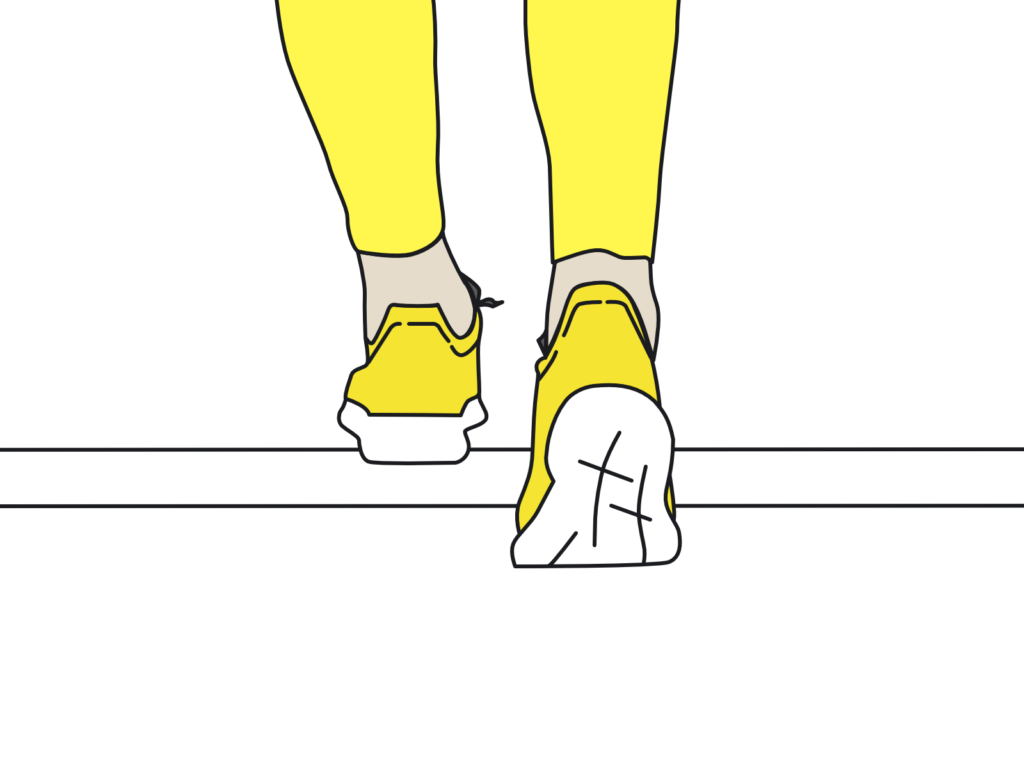
不登校や母子登校は親御さんとしても不安な経験ですが、家庭教育を通じてできることがたくさんあります。
今は親御さんも不安なお気持ちが強く、「このままでいいのだろうか?」などと焦るお気持ちも出てしまいやすいでしょう。
しかし、焦って対応してしまうと間違った対応になってしまうことが多い傾向があります。
子どもの心を支え、親自身も成長できる時間として前向きに捉えましょう。
親御さんとして子どもの為に変わる覚悟を持たれる必要はあると思いますが、あまり気負い過ぎると長続きしません。

まずはできるところから始めていけるといいでしょう。
その中でどうしても親御さんだけで抱え込むのが難しい部分も出てきます。
その場合は、誰かを頼るということも選択肢の一つとして活用していただければと思います。
相談機関は公的なところや民間機関など様々ありますので、親御さん達が安心して相談できる相手に相談されてみてくださいね。



コメント