「学校に行けているだけマシじゃない。」そんな心無いことを言われることもまだまだある母子登校。
親御さんの負担感を考えると、精神的にも体力的にもしんどい状態が続くことが多く、お仕事をされている親御さんが辞めてしまうケースも少なくありません。
ブログ読者のみなさん、こんにちは😊
今回は母子登校についての記事になります。
母子登校の背景には様々な問題が隠れていることが多い
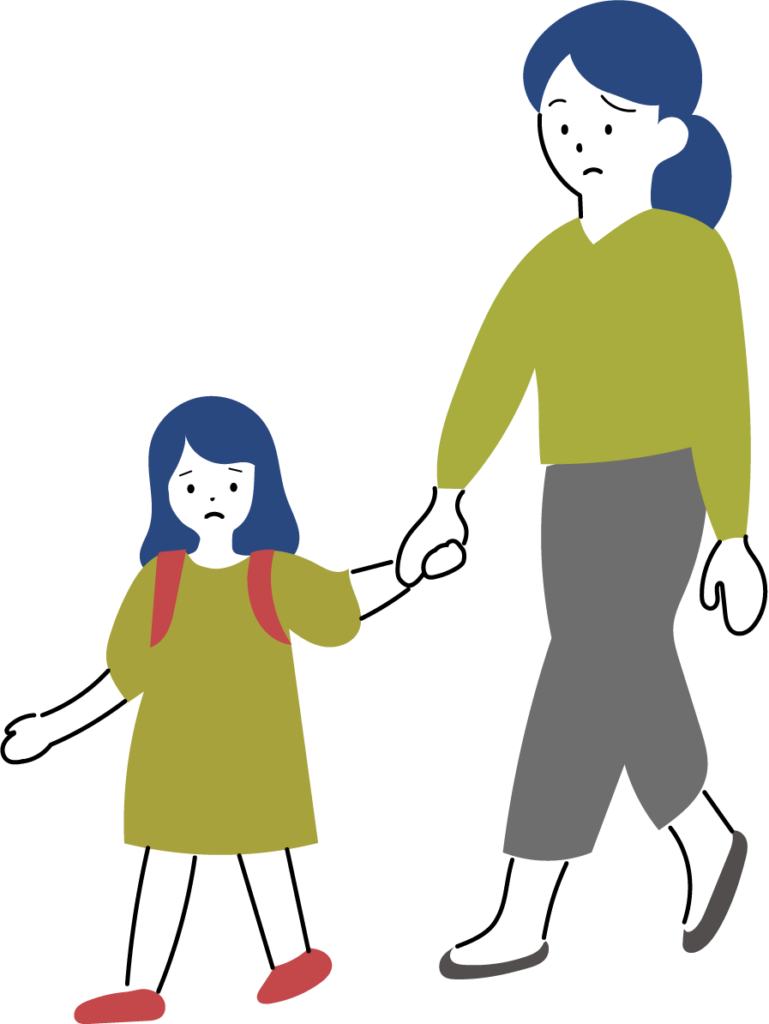
母子登校は、子どもが学校に通う際に母親が同行する状況を指しますが、この現象の背後には、さまざまな心理的な要因が隠されています。
この記事では、なぜ母子登校が起こるのか、その根本的な原因を掘り下げ、解決策を考えてみたいと思います。
不安や恐怖が根底にあることが多い
母子登校の多くの場合、子どもは学校に対して強い不安や恐怖を抱えています。
この不安は、いじめや友人関係のトラブル、学業のプレッシャーなど、さまざまな原因で引き起こされることがあります。
また、子ども本人も何に対して不安を感じているのかを理解できていないことも多く、親御さんが「学校の何が怖いの?」などと聞いても具体的なものが出ないことも少なくありません。
ひとつひとつは小さな不安であったとしても、それが積み重なれば子ども達からすれば恐怖へと変わっていきます。
積み重なった不安や恐怖は次第に「学校怖い」に変わっていくのです。
子ども達からすると学校に行くことが「未知の恐怖」と感じられるため、信頼できる母親と一緒に行くことで安心感を得ようとするのです。
親子間の分離不安
子どもが学校に通うことに不安を感じている一方で、親、特にお母さん側にも分離不安があることがあります。
お母さん自身が「子どもを守らなければならない」という強い思いを抱え過ぎてしまうと、子どもに対して過干渉になってしまうことがあります。
お母さんが我が子を守ろうと思うこと自体は親である以上自然な流れであると思います。動物の本能とも言えますよね。
しかし、子を心配してしまう気持ちが強くなり過ぎて過干渉対応になってしまうことで、子どもの成長を止めてしまうこともあります。
子どものSOSとして母子登校という形で表現されることもあるということは、知っていただきたいところです。
親であるが故の意識
母子登校が続く背景には、親の「自分がいなければ子どもはやっていけない」という親であるが故の意識が関与している場合も少なくありません。
我が子の為に身を投げうつことが苦でない方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは支援の中で親御さん達にこうお伝えします。

「目先のかわいそうよりも、将来のかわいそうを取り除いてあげましょう。」
親という立場では、目の前でお子さんが躓いている状態の時にそのまま見過ごすというわけにはいきにくいかもしれません。
しかし、目の前の子どものかわいそうを取り除くことに注力し過ぎると、子どもが問題に対して乗り越える力が培われないことがよくあります。そのまま子どもが大きくなってしまうと、大人になってから(将来)のかわいそうを取り除けない状態になってしまう可能性は往々にして考えられます。
今、子どもが親元で過ごしてくれている範囲なら親御さんの手が届き易いですが、子どもが親元離れて暮らしていくとそうもいきませんからね。
親元で暮らしてくれている間に、子どもが1人でも過ごしていけるだけの力を身に着けられると、親御さんも安心して見守れるのではないかと思います。
親の過保護・過干渉対応による影響
親御さんのお子さんに対する対応が過保護や過干渉になっている場合、子どもが自ら問題を解決する力を育む機会が少なくなり、安心できるお母さんを頼る傾向が強まります。
学校などの社会では【自分で考えて行動する】ことが求められますので、その経験が少ないお子さんの場合は「どうしたらいいんだろう・・・。」などと不安になることが多いでしょう。
その結果として「学校が怖い」となり、安心できるお母さんと一緒でないと学校でも過ごせないという状態に陥ることは多いです。
子どもに対して親が手出し口出しすること自体が悪いわけではありませんが、子どもの成長を考えて適切な距離感やサポートの度合いを考えてあげたいものです。
また、母親自身が自身の生育環境や経験から不安や自己肯定感の低さを抱えていると、その影響が子どもにも伝わることがあります。親御さん自身が気づかれていない場合もあり、苦しんでおられる方は少なくありません。まずはご自身の思考や対応の癖を理解して対応していくことが求められるでしょう。
学校や社会的プレッシャー
学校側からのプレッシャーや社会的な「普通に通うべき」という期待も母子登校に影響を与える要因です。学校側の対応が適切でない場合や、無理解な態度が不安を増幅させることがあります。
良かれと思ってママ友さんなど周りの方から言われた内容も、母子登校を続ける中で精神状態も不安定になっていると素直に受け取りにくいことは多くなります。
また、他の保護者や教師からの無言のプレッシャーが親御さんにのしかかり、「どうにかして学校に通わせなければ」という焦りを生むことがあります。
学校で親御さんがいなくとも過ごせている他のお子さんを見ていると、どうしても「私の育て方が悪かったのかしら・・・。」などと追い詰められてしまう状態になりやすいとも言えます。
解決に向けてのアプローチ
母子登校の解決には、家族全体でのアプローチが重要です。
「みちびき」では、家族全体に対してアプローチすることをシステムズアプローチと呼んでいます。
お子さんに対してだけ対応するのではなく、ご家庭全体を1つのシステムと捉えて対応策を組み立てます。
- カウンセリングや心理的支援を受ける:親子の不安や心理的な問題を解決するために、専門的なカウンセリングを受けることが効果的です。特に、親自身の心のケアが必要な場合も少なくありません。支援の中でも、母子登校をされている親御さんはみなさんものすごく頑張っておられる状態です。頑張り過ぎている場合もありますので、親御さんの心理的なサポートをしつつ、状況の整理が必要であると考えます。どこは親御さんが頑張るべきなのか、どこからは子どもに任せていった方がいいのか等、分析を踏まえたうえで具体的にライン引きをしていくことで親御さんの負担を減らすことができるでしょう。
- 段階的な自立支援:一度に問題を解決しようとする方法もありますが、その方法では子ども側の負担も大きくサポート体制がしっかりしていないと上手くいかないことも多いでしょう。子どもが少しずつ自立できるような環境を整えてあげることで、子ども側も負担を感じ過ぎず頑張れることが多くみられます。親も子どもも、少しずつ段階を踏んでサポートすることにより、親御さん側も心配に感じ過ぎない、子ども側も少しずつ「できた」という自信を持ちながら進めることができるでしょう。
- 学校との連携:学校と協力して、子どもにとって安心できる環境を提供することも必要です。教師とのコミュニケーションを密にし、子どもが学校での生活に徐々に適応できるようなサポートをお願いすることが重要です。学校側と家庭とで足並みが揃っていないと、子どもが困惑してしまうことも多いですので、学校側と協力体制が取れると親御さん側もできることが増えるのではないかと思います。
終わりに
母子登校の背後には、親子双方の心理的な要因が複雑に絡み合っていることが多いでしょう。
そこをしっかり分析しながら見極めることがポイントです。
「みちびき」では、お子さんの性格傾向や親御さんのこれまでのお子さんへの対応からどういった対応がお子さんに合っているのかを分析します。その上で、親御さんに対してお子さんに合った対応法をお伝えし、ご家庭で実践していただきます。
そうやって少しずつですが、子どもが学校という社会で生活していけるだけの力を家庭内で培っていく土台を作るイメージです。
それだけでお子さんが自立し登校面でいい影響が出ることもありますが、早期の母子登校の解決策として登校面で段階的にお母さんが離れられるような状態を作ることが重要になってきます。
母子登校に悩んでいる方々には、一人で抱え込まず、周囲や専門家のサポートを活用することを強くおすすめします。



コメント