学校に行けなくなったお子さんの姿に戸惑い、不安に感じている親御さんも多いのではないでしょうか。
この記事では、実際のケースを通じて、不登校を克服し、再登校への一歩を踏み出した親子の実例を紹介します。
事例紹介(小学4年生の男の子のケース)

A君は小学校4年生のときにクラスメートとのトラブルで学校に行きたがらなくなり、次第に登校を避けるようになりました。
A君のお母さんは、最初はただの一時的なものだと思い、数日で落ち着くと思っていました。しかし、何日経っても『学校に行きたくない』というA君の言葉が続き、その理由を聞いても『なんとなく嫌だ』としか言わないため、どう対応すればいいのかわからず不安が募りました。
お母さんは『私の育て方が悪かったのだろうか』『もっと早く気づくべきだったのかもしれない』と、自分を責める気持ちが日に日に強くなっていきました。周囲の親からもどう思われているか気になり、子どものために良かれと思ってきたことが逆効果だったのではと悩むようになっていったようです。
A君が登校しなくなると、家庭内の会話も減ってしまい、お母さんはどう接するべきか分からなくなりました。『学校に行きなさい』と強く言いたくなる一方で、逆に傷つけてしまうのではないかと怖くなり、次第に話しかけること自体に躊躇するようになりました。
お母さんは、A君がこのまま登校できなくなってしまうのではないかという漠然とした将来への不安に押しつぶされそうでした。『このまま学校に行かなくていいわけがない』と頭ではわかりつつも、具体的にどうすればいいのかが見えず、ただ焦りと苛立ちが募っていくばかりでした。
そんな時に、ネットや書籍で不登校について調べて私たちの元へ辿り着いてくださったようでした。
インテークカウンセリング(初回のカウンセリング)

初回の電話カウンセリングでは、まず親御さんからの状況の聞き取りから始まりました。
不登校に至った流れや、その後のA君の様子やお家での過ごし方等・・・親御さんからわかる範囲でご説明いただきました。Aくんも不登校になったことによって生活がガラリと変わってしまったので、A君なりに苦しんでいるのだなというのが親御さんの話でも見えてきましたし、それと同様に親御さん自身も苦しんでおられる様子が伺えました。
初回のお電話で親御さんが話されていたのは、「息子さん(Aくん)に対してどのように接していいのか分からない。」ということでした。ネットや書籍で不登校の対応など様々書かれてありますので、親御さんはそれらの対応を家庭でも実践してみたようです。
例えば、不登校は子どもの心のエネルギーが溜まっていない状態なので溜まるまで待ってあげましょう・愛情を注いであげましょうと書かれてあれば、Aくんからの要求はなるべく聴いてあげるようにしていたようです。しかし、それを続けていても最初はAくんが落ち着いてきたようにも感じたようですが、継続していくうちにどんどんAくんが我が儘になり、癇癪を起すことも増えていったそうです。
親として我が子であるAくんのことが大事ですし、これからのAくんの人生を考えると不安や心配が募る思いがあるものの、どうしたらいいのか正解が分からないという点でご自身の対応に悩む日々が続いていたということでした。
そこで私たちからお伝えしたのは、

Aくんの復学ももちろん考えていきたいところですが、そこよりも親御さん自身がAくんに対してどう接していけばいいのか、具体的にどこまで親御さんがサポートしてあげてどこからAくんに任せていくのかというライン引きをしていきたいですね。
という内容でした。つまり、復学に向けてのサポートだけでなくご家庭での親子間の関わり方に対してサポートが必要であるとお伝えしたのです。
具体的な支援ステップ

家庭でどのようにAくんに対して対応していくのかを、お子さんの様子やご家庭の状況などから分析して具体的にアドバイスしていきました。
ここでは、アドバイスした内容の中でもいくつかピックアップしてみます。このブログ記事を見てくださっているご家庭でも活用できる内容もあるかと思いますので、参考程度に見ていただければと思います。
子ども上位な対応を避ける
A君が不登校状態になってから、親御さんは愛情を注ぐという点を注視し過ぎて子どもが望むこと殆どにOKを出すようになっていました。それだけでなく、何事においても家庭内ではAくん優先の状態が続き、次第にAくんは自分の思い通りにいかないようなことがあると、癇癪を起すようになり親御さんも手を付けられない状態が続いたそうです。
Aくん以外に兄弟姉妹が居ないご家庭だったので、どうしてもAくんを優先されるような環境下にあったとも感じますが、支援の中では親御さんの都合は優先していただくようにお伝えしました。
兄弟姉妹がいないご家庭では、子どもの我慢力が低くなってしまうのでは?という不安を抱えておられる親御さんは少なくありません。お気持ちはわかりますが、兄弟姉妹がいるから必ずしも我慢力が強い子が育つという話ではないのでご安心ください。ただ、Aくんのように一人っ子のご家庭では兄弟姉妹がいるご家庭に比べると我慢をしなくても済む状況が多いというのも事実です。ですので、子どもが小学生以上に育ったご家庭では、少しずつ親御さんの都合を優先する場面を作ることが望ましいでしょう。そうすることで子どもは自然と我慢するタイミングが生まれます。
親が子どもに対して指示や提案をし過ぎない
子どもというものは、先を見通す力が低いことが多く、親から見るとどうしても甘い選択をしてしまいがちです。「なんで今それをするの?」「これ先にやった方が早いわよね」これらは多くの親御さんが子どもを見ていて感じることです。(笑)
ただ、ご家庭内で親御さんが「あれしなさい」「こうした方がいいわよ」「こうしてみたら?」などと指示や提案が多いと、子どもは次第に自分で考えて行動するということをしなくなっていきます。そりゃそうですよね。自分で考えなくとも親御さんが親切丁寧に教えてくれるわけですから。人間は楽なことを見つけるのは上手で、それはどの子も基本的に変わりません。
しかし、学校では自分で考えて行動することを求められることは多いです。その為、それらが日常的にできていないと学校で不適応を起こしやすい状態になっていくでしょう。実際、Aくんは学校の授業で自分で考えて行動するような場面(例えば、自由工作や作文を書くなど)では、苦手に感じることが多かったようです。
親の都合を優先する場を設ける
子どもが生まれると、基本的に子ども優先になるご家庭は多いと思います。それが自然なことだと思いますが、社会では常に自分の都合が優先になることはありません。子どもが小学生以上になるとその辺りも少しずつ教えていくことが大事であると考えます。
Aくんのご家庭では、Aくんが「○○したい!」などと言うと親御さんがその時に家事などをしていても手を止めて付き合ってあげる場面が多くみられました。Aくんは兄弟姉妹が居ないご家庭だったので、親御さんが常にAくんの都合に合わせてあげていた状態では日常生活の中でAくんが我慢をする場面が少なかったのです。この状態が日常化していると、学校生活などの集団生活では自分の思い通りにいかないことの方が多いですから、違和感や「嫌だな」という気持ちにもなりやすいでしょう。
家庭では、常にAくんの要望を断るという話ではなく、親御さんの都合を優先する場面を設けて自然に家庭内でAくんが我慢力を身に着けられるような環境を作っていきました。
親の考えや姿勢を子どもに伝える
ある程度家庭内でAくんの様子が落ち着いてきたのを確認してから、親御さんからAくんに対してこれからどうするのか?という点を話していきました。このままの状態でいいのか?やこれからどうしていくのか?などを話していくことを私たちの支援では【登校刺激】と呼んでいます。登校を刺激するような話を親子でしていったということです。
これらの話をする際には、基本的に親子間でそういった話をしても子どもが聞いてくれる関係性であることがまず大事になります。Aくんの家庭でも登校刺激となる話をすることができる関係性があるのかというのは分析したうえで、もう少し親御さんの立場をあげていく対応も具体的にお伝えしていきました。
それだけでなく、登校刺激の場で話す内容から親御さんと子どもの立ち位置まで細かく綿密に親御さんと相談しアドバイスします。数が多いとは言いませんが、この登校刺激をすれば子どもは変わると勘違いされている親御さんは一定数いらっしゃいます。しかし、私たちがこれまでお伝えしているように、子どもが急に学校に行きだす等という魔法のような言葉や対応というのはありません。それを謳っている支援団体があれば怪しいと思われた方がよいでしょう。
家庭での対応を変えることで見えてきた変化
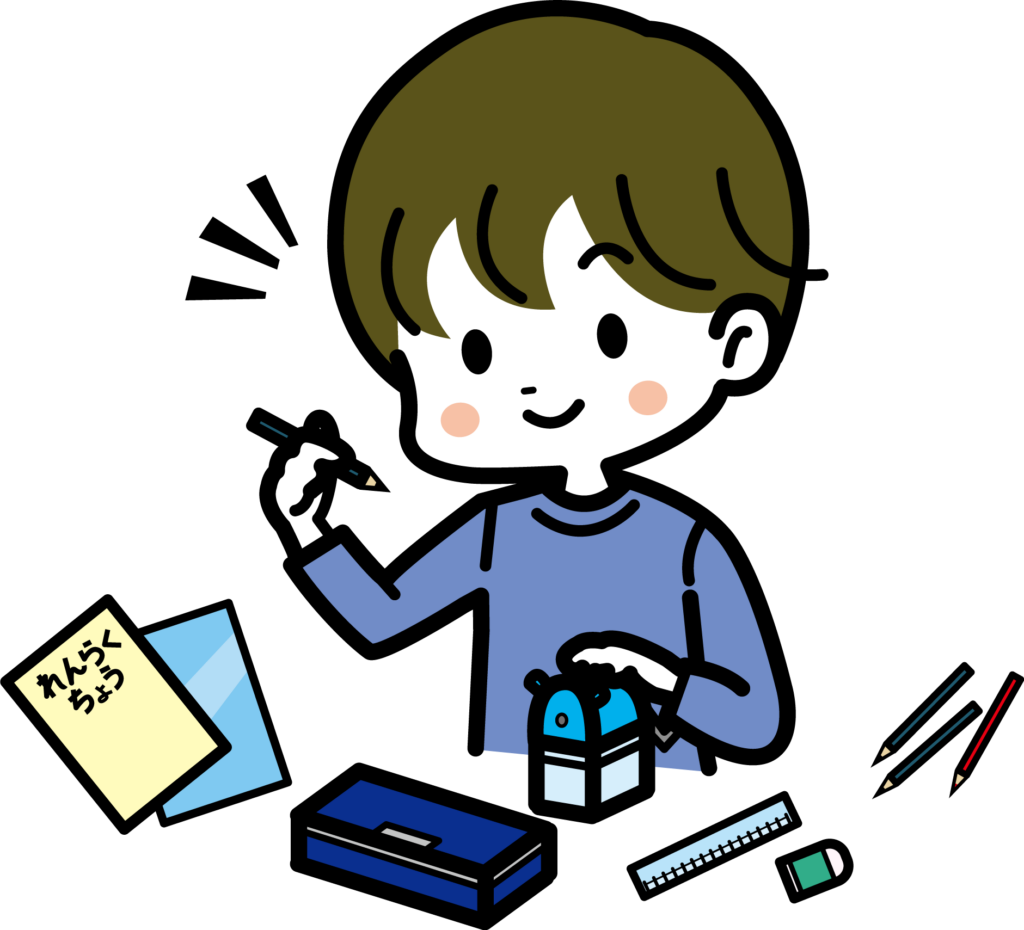
家庭の対応を変えていくことにより、Aくんは自分で考えて行動するようになりました。それだけでなく、これまで思い通りにいかない時は癇癪を起していたAくんは、自分で自分の気持ちに整理をつけ落ち着かせることもできるようになっていきました。
親御さんとしては、私たちのアドバイス内容が目から鱗の内容が多く、本当に我が子に合うのか?と思うこともあったようです。しかし、対応を続けていくと少しずつそして着実に子どもがいい流れで変わっていくのが分かりました。子どもがいい方向に変わっていく様子を見て親御さんは「ここに相談してよかった。」と思ってくださったようでした。
また、Aくんだけでなく親御さん側の捉え方や親としてのマインドも変わってきたと話してくれました。これまではAくんが失敗しないように、困らないようにと親御さんはサポートしなければいけない、それが親なんだと思い対応されてきたそうです。親であれば誰しもそう思うと思いますし、そう思えることは素晴らしいですよね。
しかし、Aくんが不登校の状態が続き親御さんも対応をネットや書籍で調べる中で、そうすることでAくんが親が居ないと生きていけない子になってしまったのではないか?と思うようになったそうです。善かれと思ってしてきたことが、子どもの成長を奪ってしまっていた可能性があるということを知り親御さん達は驚かれたようです。
支援を通じてAくんがこんなにもできる力があるんだ!ということに気づいたことが何よりも親御さんが嬉しかったことでした。Aくんが不登校になり、親御さんに甘える姿も多くなっていたので、いつの間にか親御さんの中で「Aくんの為にあれこれやってあげることが親の務めである」と捉えるようになっていました。それが今では、「親が近くにいなくても安心して見守れる存在」に変わったことで、親御さん側の精神的な負担も軽くなられたようでした。
復学してからの様子

復学を果たしてから、Aくんも頑張っていましたが学校に行けば行ったで起こる問題もあります。
学校に行ってからの問題として挙げられるのが、
- お友達関係のトラブル
- 勉強面の問題
が多いでしょう。
Aくんは自分から自分の意見や「嫌だ」などと言うことが苦手だったので、学校生活の中で嫌な思いをしても上手く断ることや自分の意見を伝えることができませんでした。常に我慢をしてしまうという状態が多かったです。しかし、不登校前と復学後に大きく違ったのは、それらの不満を家に帰ってからお母さんに話せるようになったのです。そのお陰で、お母さんと一緒に「どうすればいいのか?」という解決策を一緒に考えていくことができました。お母さんとの相談を繰り返す中で、Aくんも勇気を出しながら学校で先生やお友達を頼りながら問題を解決していくことができました。
また、勉強面では最初からみんなに追いつくというところを意識するのではなく、授業で習っている範囲を少しずつ理解していくことを意識して家庭では対応していただきました。つまり、足りない部分を補う対応ではなく今の学校に行き続けながら解決できる方法にしていきました。
学校生活に慣れるまでは、学校側にもお願いし宿題をしなくても叱らないでくださいなどの配慮をお願いしていました。そこから、学校が慣れてきた頃に少しずつ追いつくための勉強も家庭や学校の先生のサポートがありながら少しずつ取り入れていきました。そうすることでAくんも無理のない範囲で頑張り、少しずつそして着実に学校に行きながら解決していく術を身に着けていってくれたように思います。
私たち『みちびき』の支援は、復学がゴールではありません。
子どもの自立の為に、復学はあくまでも通過点です。子どもが親元離れて生活していくまでの間に、何かあっても自分で考え・行動しながら(時には周りを頼りながら)解決していける力を身に着けていくことが大事であると考えます。そう育ってくれると、親御さん達も安心して子ども達を見守ることができると思うのです。子どもの成長はすさまじく、親ができないだろうと思っていることでも子どもは踏ん張れることも多いです。
どうか、今の現状に不安を抱えておられる方、将来が見えないと嘆かれている方・・・専門家に相談することも解決策の1つであると捉え、頼ってみてくださいね。



コメント