不登校の数は年々増えていき、不登校の居場所も増えていきました。
そんな中、復学支援だけではなく様々な考え方・捉え方が増えていき、いつしか復学支援という手法に対して冷やかな意見も出るようになってきたように思います。

みなさん、こんにちは。
今回は復学支援を15年続け現場を見続けた立場からお話したいと思います。
あくまでも私個人の見解でありますが、この15年間多くのご家庭と不登校のお子さんを見てきたからこそお伝えできることがあると考えています。
メディアでも近年不登校を取り上げることはありますが、ほんの一部しか紹介されません。
そのせいで偏ったイメージが先行しているように危惧しています。
今回のブログ記事が読者のみなさんの参考になればと思います。
不登校になったことによって抱える不安が増える

多くの不登校児を支援を通じてみてきましたが、まったく同じ内容だったケースは1つもありません。
しかし、共通しやすい部分は出てくるものです。
その一つが【不登校になったことによって多くの悩みを抱えてしまう傾向にある】ということでしょう。
不登校期間が長期にわたると、休みはじめにはなかった
- 将来に対する不安
- 「このままで本当にいいのか」という不安
- 「自分はこのままどうなってしまうのだろう」という不安
など具体的な不安というよりも漠然とした不安を抱き始めます。
そして、「このままではいけない」と子ども自身が学校に向けて動き出そうとしたとき、今度は学校に行く上での具体的な不安が襲ってきます。
例えば…
- クラスのみんなに自分はどう思われているのだろう?
- 授業は今どこをやっているのだろう?
- 自分の座席は?
- 今更戻って勉強はついていけるのだろうか?
…などなど、休んだことによってわからないことだらけの状態になってしまいます。
わからないことが多い状態というのは、大人であってもストレスです。
子どもたちはストレスやイライラを親や家庭に向けて暴力や物を壊してしまったり、現実逃避のために昼夜逆転状態になったり、わがままになりがちです。
学校に行っている間には上記のような行動をしていなかった子たちでも、学校を休み続けることによるストレスで変わってしまうケースは珍しくありません。
私たちが復学支援を行っている理由はまさにここです。
「子どもが変わってしまうことが問題」ということ。
不登校に対する考え方の変化
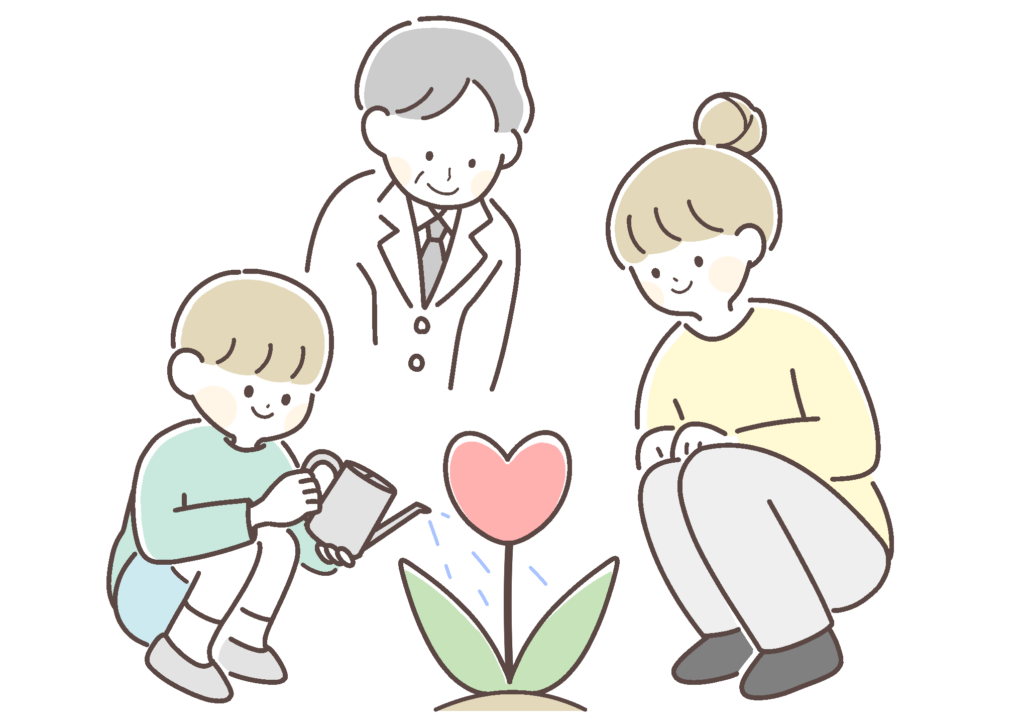
私は不登校復学支援に携わり気付けばもう15年以上が経過していました。
この15年の間に不登校に対する世間の考え方は大きく変化したように思います。
一番大きな変化は「学校がすべてではない」ということかと思います。
実際支援をしているとすべての不登校の子どもたちが学校に行くことが正解とは私も思いません。
学校以外の居場所や学校を休んでしばらく英気を養う必要がある子がいることは支援をしていてそういうケースもあることは実感しています。
しかし、すべての不登校の子ども達がそれにあてはまるわけではないのではないかと私は考えます。
ちょっと休んでまた頑張ろうと思っていた子がそのちょっと休んだことで再び登校することが怖くなってしまったとか、子どもの環境適応力の問題で不登校になるケースなど、その問題さえ解決してあげれば学校に再び登校できるケースも少なくないと思います。
それをしっかりした分析もなく、学校に行けていないのであれば、他の居場所やゆっくり待ちましょうという対応を通り一辺倒にしてしまっていると、逆に不登校が長引いてしまっているケースも少なくないと思います。
なんでもかんでも休ませましょう、他の居場所もありますよでは解決しないケースがあると思います。
捉え方の変化は不登校の数が増えたことも影響している
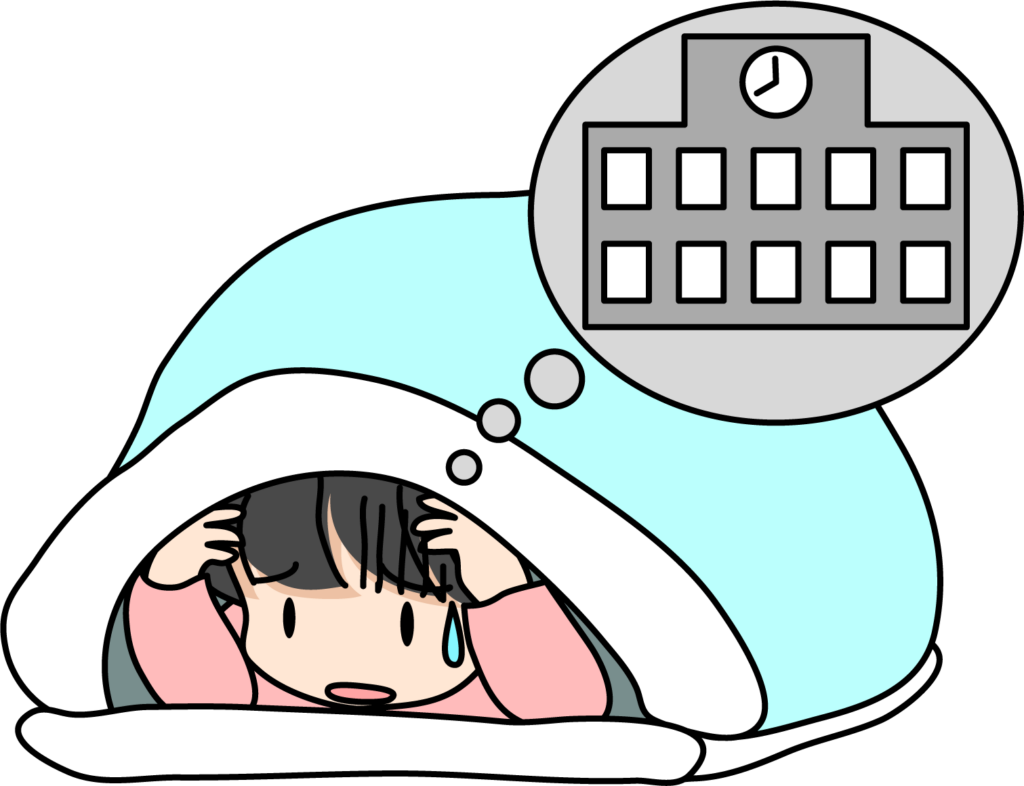
学校の環境も不登校の数が増えていることで、学校は休んでいてもいいよねという雰囲気がそこにできているようにも思います。よい意味でも悪い意味でも不登校にみんなが慣れていっている雰囲気はあるのだろうと思います。
そうなることで不登校を選んでもなんとかなるだろうと安易に考えた結果、どうにもならなくなってしまっているケースも多くなっているように思います。
どうにもならなくなってしまった後だと、いざ不登校から動き出そうとしてもどうしたらいいかわからず、家庭の外の環境に入ることを極端に怖がってしまい、家から出ない選択を取らざるをえなくなってしまうケースも少なくないと思われます。
この場合は前向きに選択しているわけではないので、不登校中の子どもの様子が悪くなっていってしまうケースが多いように思います。
ただ、この場合は社会の環境の方の問題なので、その環境を変えることは難しいと思います。その学校環境だからこそ救われる子もいるのも事実であり、その環境が適さない子だけのために環境が変わるということはなかなかないところです。
子どもたちを取り巻く環境は刻一刻と変化していきます。
その変化に不適応を起こしてしまった場合には、適応能力を伸ばすのかあるいは個を尊重し自立できるような環境を整えるのかが求められると思います。
「みちびき」が考える復学支援

私たちは「学校はどんな状況であっても、どんな子でも毎日必ず行くべき」とは思っていません。
休まなくちゃいけない子も多くいることも確かです。
しかし、不登校になってからずっと不安な気持ちを抱えたまま生活していくことを考えると、それこそその子が「かわいそう」だと考えます。
こういったケースの子どもたちは「休んでいい」という事を認めてほしいのではなく、「本当は学校に行きたい」と思っていることが往々にしてあります。
でも、「学校に行けない」「行くにしてもどうしたらいいかわからない」といった葛藤をしている子どもたちが多いのです。
この不安から解放してあげるためにも学校という場所に戻り、学校生活を送ることでこういった行動が治まっていく姿を私たちは何度も見てきました。
不登校は学校に行かないことだけが問題ではないと私たちは考えています。
1人でも多くの子ども達を笑顔にしてあげたい。
そのような思いで、今日も私たちは全力で支援をしています。
アセスメント(分析)の上、適切な支援を

ケースによりしっかりした分析のもとで、その不登校をしている子どもの家庭の状況や学校での様子、その子自身の特性など、その子がこれまで生きてきた背景や取り巻く環境を分析して、その子に合う、その家庭に合う支援を届けてあげる必要があると思います。
それが、学校以外に居場所を確保してあげる必要がある子もいるし、家庭の中で過ごさせてあげる必要のある子もいる、そして復学を目指すためにサポートが必要な子もいると思います。
しっかりしたアセスメントがあって支援を考える必要があるのだと思います。
「学校がすべてではない」にしろ、ケースによってしっかりと分析したうえで必要な支援を考えてあげる必要があるのではないかと思います。
なによりも子どもたちが不登校だとしても前向きに生きていけるように、不登校であることが前向きに生きることを阻んでしまう要因なら解決してあげる必要があり、その解決法が様々ある中でどの手法が適切かしっかり判断していくことが求められてきていると思います。
まとめ
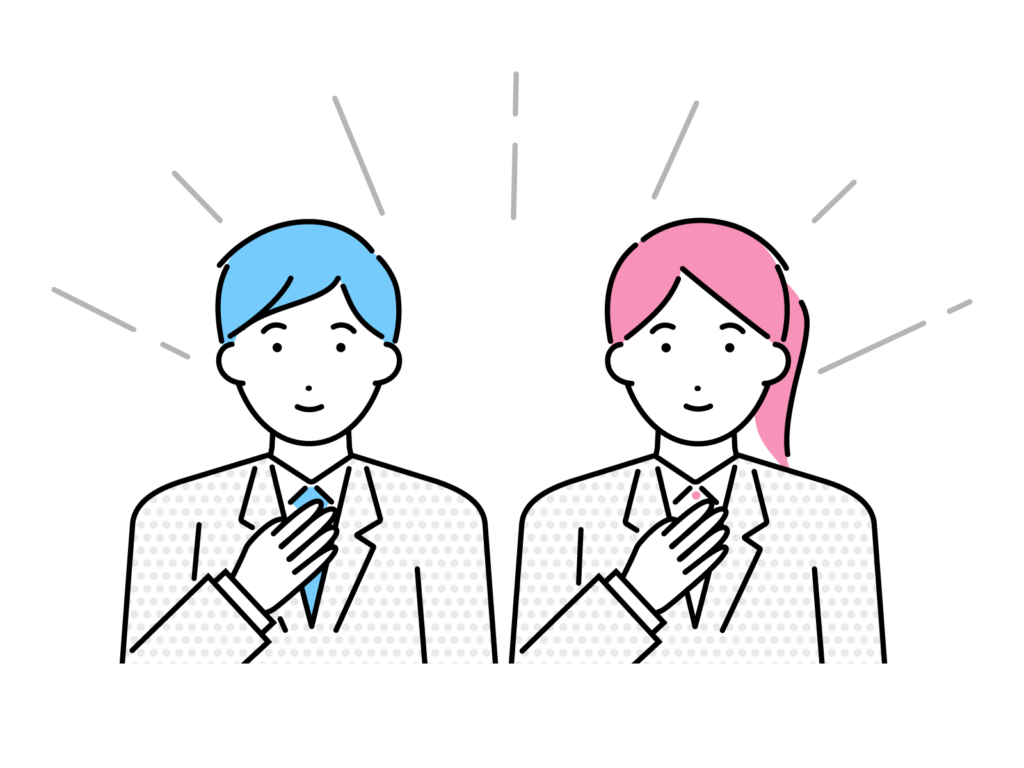
どちらにせよ子どもたちを取り巻く学校の環境も変化していることを私たちは知っておく必要があると私は思います。
私たちは復学を目指す支援をしていますが、復学がすべてではなく学校に行こうが行かまいが子どもたちが前向きに楽しく生きていける環境が整っていくことを願いつつ、支援に携わる限りは一件でも多く子どもたちや家庭が明るく笑顔で過ごせるように寄り添う支援をしていきたいと考えます。
親である以上、我が子が不登校になったときにショックを受けることや焦られることもあると思います。これは支援の中で多くの親御さんにお話を聞いてきた私たちだからこそ分かることでもありますが、どの親御さんであっても不安や焦りを感じておられます。それ自体が悪いという話ではないのですが、お子さんに対する対応を組み立てる際は、親御さんのお気持ちと分けて考えていく必要があります。
それを自身でできればいいのですが、お子さんを目の前にすると感情も影響して上手く切り分けて対応することができないことも多いと思います。そういう時は、親御さんだけで抱え込むのではなく客観的な視点がある方がスムーズな場合もありますので、公的な相談場所や私たちのような民間機関などで相談されることをおすすめします。



コメント