
みなさん、初めまして!
ひと昔前に比べると、不登校の支援というのも様々な考え方・手法が生まれ、多くの方が支援者として活躍されているように感じます。
考え方や手法は様々ありますが、どういった方法が我が子にマッチングするのかを見極めるのは本当に大変ですよね。
子育てに悩む親御さん達に、私の支援がどのようなものなのかしっかり明示しながら支援を受けられるのかなどご検討いただきたいと思っております。
まずは「みちびき」がどのような想いで支援を差し上げているのかお伝えしたいと思います。
年々増える不登校の数
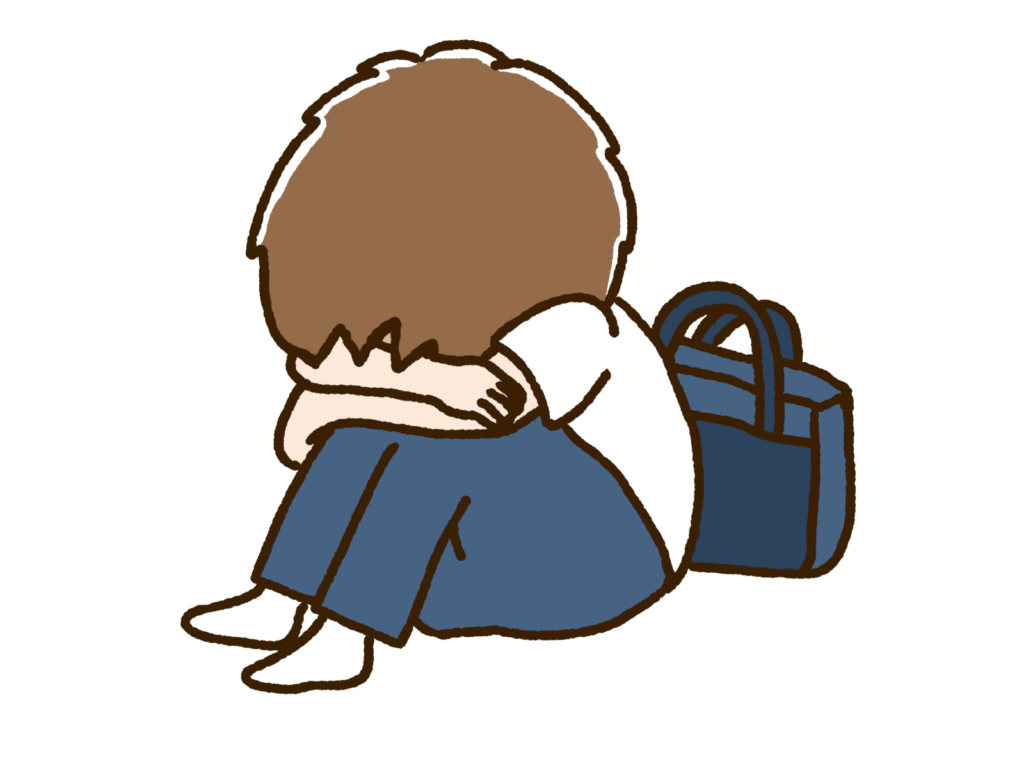
私自身、支援者としてもう9年目に突入しました。
私が支援者として歩み始めた頃に比べると、随分不登校児童生徒数の数は増えましたし、世間的認知も広がりました。
文部科学省の令和4年度の調査報告書によると、小・中学生の不登校児童生徒数は約30万人(299,048人に)も及びます。
また、その中でも90日以上欠席が続いている児童生徒数は半数以上(165,669人)にも及びます。
つまり、不登校は長期化している傾向にあり、解決していないケースが半数以上あるということが文部科学省から発表されたデータでも読み取ることができます。(令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について)
毎年子どもの数は減っているのに、不登校児童生徒数は増え続けている・・・そんな状態に国も平成28年12月に義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律として「教育機会確保法」が公布されました。(文部科学省出典:「教育機会確保法」って何?)
この「教育機会確保法」ができたことにより、これまで不登校児童生徒に対して学校という場でしか勉強をする場がなかった子どもたちにとっては、勉強ができる環境や場所が増えたと思いますし、不登校であることを受け入れて学校などでも配慮(合理的配慮)をしてくれるようになりました。
一昔に比べると、学校に行けない子ども達が学校とは違う別の場所で活躍しているという情報も耳にしたりします。
一方、メディアでは登校を促すことが悪と捉えられるような報道も目立ち、いつしか「学校に行かなくてもいい」という考え方が世の中に広まっていったように感じます。
出口が見えない苦しさ

「無理して学校に行かなくてもいいじゃない。生きてるだけで十分よ。」
不登校のお子さんを持つ親御さんが、ママ友や職場の方などに相談したときに言われた言葉だったようです。
この言葉をおっしゃった方は悪気があったわけではないと思います。
きっと相談者さんを励ますおつもりでおっしゃったようにも感じますが、言われた当人からすると「そうよね。」と思う反面、「本当にそうなのかしら?」と不安に駆られたと話してくださいました。
そうですよね。
周りの同学年の子ども達は毎日当たり前のように学校に登校するのに、居るはずのない我が子だけが毎日家の中にいる。
「生きてるだけでいいんだ・・・。」そう思いたい気持ちもあるのにどうしてか「本当に・・・?」という疑念が湧いてくる。
その疑念は少しずつしかし着実に親御さん側に積もっていきます。
どうにかしたくても学校のスクールカウンセラーや公的な教育相談で言われることはみんな口を揃えたかのように「お子さんの心のエネルギーが溜まるまで待ちましょう。」です。
そう言われて親御さんも一度はそう思うのですが、多くの方が「このままでいいのだろうか?」「いつまでこの状態が続くのだろう・・・。」そう不安に思われてご相談される方ばかりです。
また、これまでの支援の中で出会ってきた不登校の子ども達も、「どうしていいのかわからない。」という思いで身動きが取れなくなっている子が殆どでした。
それぐらい、当事者の子どもも、その親御さん含めたご家族もみなさん不安とつらいお気持ちで押し潰されています。
何度ご相談されている親御さんや子ども達の涙を見てきたか・・・。
このつらさは経験してみないとわからないことではありますが、そばで支えてきた支援者だから見えるものでもあったと思います。
問題解決に向けて何に一番着手しやすいか

不登校にはそれぞれ背景が異なり、原因やきっかけも異なります。
ですので、一概に「これをすればいい!」という魔法のような方法は残念ながらありません。
また、学校に行けない子ども達を受け入れる学校側に対応などを変えてもらおうと思っても、学校というシステムの中では即座に変化ができない状態であると言わざるを得ません。
ひと昔に比べると学校側も随分柔軟に対応してくださる学校があることも支援の中で耳にするものの、「えっ、まだそんなことやってるの?」と時代に逆行した対応をされている学校があるのも事実です。
そうなってくると、学校や環境を変えるというのは相当な時間と労力もかかり着手しやすい部分とは言い難いでしょう。
どこが一番変化を与えやすいのか?という部分を考えると・・・
やはり家庭になってきます。
家庭での環境は、親御さんを含めてご家族が一丸となって対応することにより、子どもが苦手としている部分などを工夫次第で乗り越えていけるような流れというのも作ることができるのです!
だからこそ「みちびき」では大きな声で言います。
家庭を変えることで子どもが変わっていくと。
その為には、多少のテコ入れ程度では変わらないことも多いです。
家庭のを変えたとしてもすぐに変化が見られないことも多いですが、諦めずひとつずつ着実に変えていくことでお子さんが変わってくることは大いに考えられます。
「どうすればいいか分からない」と思われる方に具体的な方法をお伝えしています。
親が変わるということ
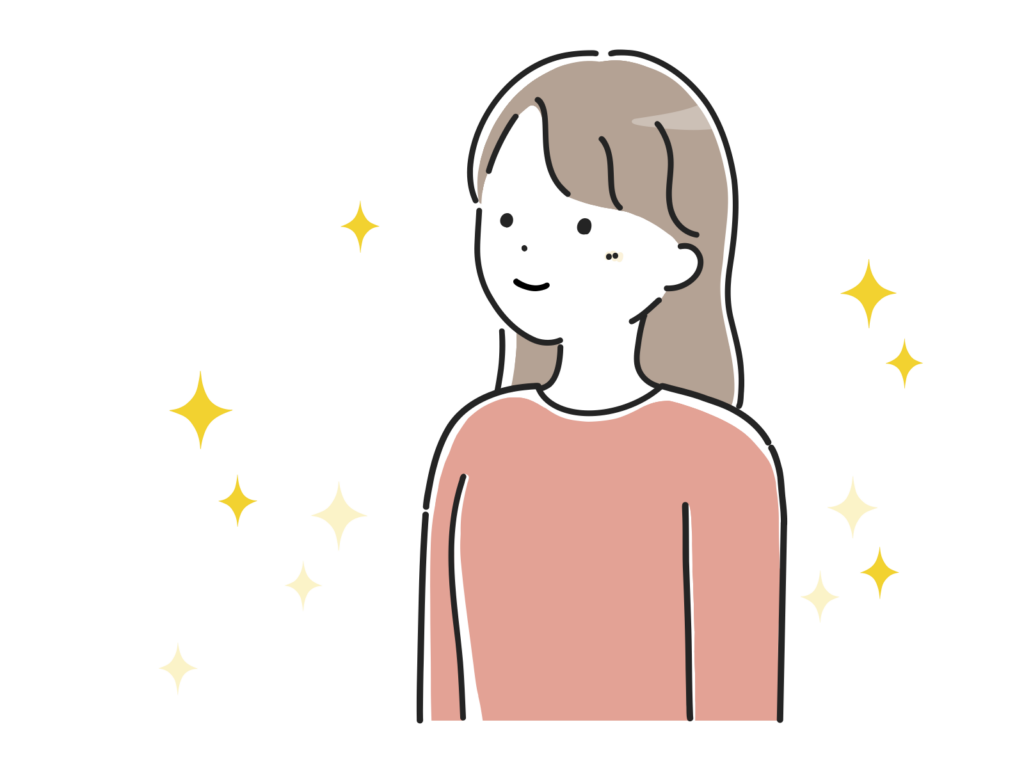
「親の対応を変えていきましょう。」
と伝えると、ネガティブに捉えてしまう人ももしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか。
ネット上では「私の育て方がわるかったの?」「これ以上私を責めるだなんて・・・。」などという意見を目にしたことがあります。
しかし、私たち「みちびき」は親御さんがこれまでされていた子育てのやり方を悪かったとは思っていません。
むしろそうせざるを得ない状態であったのかもしれないなと思いを馳せ、ご相談いただいた内容からご家庭の様子をイメージしていきます。
実際、これまで相談していただいた親御さんのお話を聞いていると、お子さんの状態や様子、そしてタイプや性格傾向、または病気などから過干渉や過保護対応にならざるを得ない状態であったと感じることは非常に多くありました。
そして、私たちのような民間の支援機関に辿り着く親御さん達は、愛情不足ではなく愛情たっぷりな親御さんばかりでした。
我が子に愛情はあるものの、どうしてあげればいいのか分からず迷われていました。
親御さんもお子さん達の為に一生懸命ネットや本などで対応を探されます。
しかし、情報がありすぎて我が子には何が適切なのか?我が子にはどの道が相応しいのか?親だからこそ真剣に悩み苦しまれている様子を支援者として一番近い場所から見てきました。
悩んで当然なんです。悩むことが悪いとは思いません。
ですが、悩みすぎておひとりで抱え込みすぎて親御さんが疲弊してしまうような状態なのであれば、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
伴走型支援

伴走型支援というのはあまり耳にしない言葉かもしれません。
一番身近な“伴走”という言葉は、マラソンなどに使われます。
ここで言う伴走型支援とは、支援が必要な人が自立に向けて、その人に寄り添いながら共に歩むような支援の形を指します。
不登校支援の現場では「課題解決型」の支援が不登校の子どもを持つ親御さんに支持され、民間機関も増えていきました。
確かに「課題解決型」の支援は重要ですが、それだけではすべてを網羅するということは残念ながらできません。
その理由としては、そもそも親御さん側が見えていない・気づいていない潜在的な課題が放置されている場合が多いというのが挙げられます。
支援の中でも親御さんからご相談いただく内容だけでは問題解決に至らないことが多く、潜在的な課題に気づけていない場合も少なくありません。
伴走という形で親御さんやお子さんを含めたご家族に寄り添いながら、支援の中で課題設定を行い問題解決に向けてサポートしていきます。
あくまで走る主体は当事者であるクライエント自身であり、伴走者は当事者が走れるようにサポートをしていくというものです。
当事者であるクライエントと相談をしながら、最終的にはクライエント自身が自走できるような形を目指していきます。
私たち支援者に依存するのではなく、あくまでもクライエント自身が自立できるような形を目指していきます。
私はよく支援の現場で親御さん達にこう伝えることがあります。

「病院と近い形であるととらえてください。病院のように治療は私たちにはできませんが、必要な時にご活用いただく支援機関であると考えています。一番いい形というのは、私たちが居なくとも親御さん達の力で、ご家族の力だけで困難を乗り越えていけるだけの力をつけていただくことです。」
カスタムメイド型の支援

私たちの支援では、ご家庭やお子さんに合った対応を組み立てながら支援を展開していきます。
その為、ご相談いただいてすぐに「こうしてください!」などと断定的に対応をお伝えすることはございません。
これまでの支援の経験や知識などからある程度分析や推察することはできます。
しかし、確定で申し上げるということはリスクが高く、支援者という立場だからこそ私たちは慎重に判断します。
私たちの支援では、どのご家庭にも分析期間を頂戴しています。
お子さんの性格傾向やタイプそして特性などと、親御さんのタイプや性格傾向そしてこれまでのお子さんに対する対応の傾向など、また原因や課題点がどこにあるのかなど分析します。
何故このように分析期間というものを設けるのかと言いますと、お子さんそれぞれのタイプや性格も違えば、不登校になった原因もさまざまであるからです。
これまで多くの不登校のご家庭に支援を差し上げてきましたが、1つとして同じケースはありませんでした。
だからこそ、私たちはそれぞれのご家庭に合ったカスタムメイド型の支援を展開しています。
あなたのお子さんに合った対応を一緒に探していきましょう!


コメント